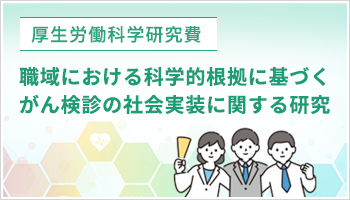領域の歴史
歴史
初代
現在の衛生学・公衆衛生学領域は、開学した1974年に衛生学、公衆衛生学、病院管理学の3講座体制にてスタートした。衛生学には重田定義教授、香川順助教授(東京女子医科大学教授に転身)、百渓浩講師、相川浩幸助手、公衆衛生学には春日斎教授、長谷部昭久助教授(1981年から杉田稔助教授(東邦大学医学部教授に転身))、松木秀明助手(本学医療短大教授)、逢坂文夫助手、病院管理学には、尾崎恭輔教授、鈴木 荘太郎助教授(東邦大学医学部教授に転身)にて始まり、1990年に本学出身の吉田貴彦先生が衛生学に加わった(旭川医大医学部教授に転身)。多くの人材を他学の教授として輩出していた。

2代目
1992年より岡崎勲先生が第2代の教授に就任され、講座も再編され地域・環境保健系地域保健学部門と環境保健学部門となり、1995年本学出身の古屋博行先生が助手として加わった。積極的に国際保健を推進しWHO,JICAなど協力施設となり、1998年木ノ上高章先生が加入して大学院医学研究科国際医療保健協力センターとして世界各国の公衆衛生学の発展の重要な役割を担った。さらに岡﨑先生は、肝臓線維化防止の研究に関しても積極的に人材をリクルートして、1995年渡辺哲先生、2002年に稲垣豊先生(後に基盤診療学系再生医療科学教授へ)が加わり肝臓の線維化予防を主体とした研究を進めた。

3代目
2006年3代目教授に渡辺哲先生が就任され、後に分子環境予防医学センターへと役割が変更し、分子生物学を予防学にも応用した新たな領域を開拓した。
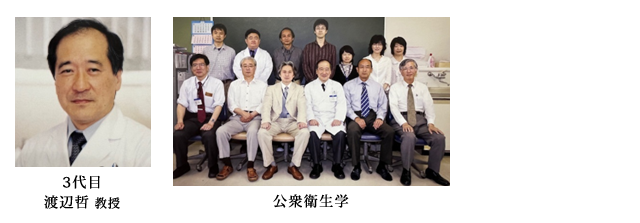
4代目
その後、2013年に第4代教授として立道昌幸が着任した。講座制廃止により名称も、2003年 から基盤診療学系公衆衛生・社会医学、2005年から公衆衛生学、2018年より衛生学公衆衛生学と変遷して現在に至る。開学当初14名でスタートした本領域は、私が入職した当時は5名まで減少したが、坂部貢医学部長のご英断により社会医学の重要性を認識頂き、現在7名体制にて教育、研究、社会貢献に尽力している。

教育面での取り組み
教育面では、衛生学は環境医学へと進化し、政策を司る公衆衛生学は、母子保健、学校保健、成人保健、高齢者保健、国際保健が中心であったが、この50年の間に医療倫理、医療制度、保険制度などの変遷にともなった医療経済的視点はもとより、対象疾病が、感染症から非感染症(NCD)すなわち生活習慣病の予防へと大きく変化する中で、国民のヘルスリレラシーを上げることの重要性が問われ、医師が患者を含め一般住民への健康教育を行う場合のヘルスコミュニケーションの技能や、保健指導など健康生活への行動変容を求める行動科学がコアカカリキュラムに入った。この間、少子高齢化が急速にすすみ、高齢者の医療、保険、介護に関する新たな制度設計がされ、医療法による地域医療構想についても随時更新されることからこのキャッチアップに努めた。また、研究手法において疫学が学問体系として確立したことも大きく(1991年日本疫学会発足)、EBMの概念がスタンダードとなり、疫学の重要性が増して国家試験でも多くの問題が出題されるようになった。また、近年では地震、豪雨などの天災に加えて、新型コロナウイルスのパンデミックに代表される災害保健が新たな分野となっている。このように社会医学は、まさに社会の変遷・変動をいち早く察知して医学教育に落とし込むことの連続であった。
50年後の未来へ
次の50年に向けた衛生学・公衆衛生学の未来は、さらに多様な変革と挑戦が必要であろう。急速に進行する人口構造の変化は、高齢化社会・ダイバーシティに対応した研究と公衆衛生教育の再構築を促し、常にアップデートされた視点でのアプローチが必要とされる。同時に、地球規模で進行する気候変動は人類の健康に直接影響を及ぼし、planetary healthの重要性が一層増していくであろう。研究面では、従来の疫学や実験医学によるエビデンス構築に加え、基礎研究結果から社会実装研究まで如何にスピードをもたせるかが重要で、実際の政策や介入に直結する成果が求められる。ビッグデータ解析やAI技術の進化は、予防医学と公衆衛生の新たな道を開き、精緻なリスク評価や効果的な介入策が実現可能となっていくであろう。これの実現のためには、領域内外、学内外、国内外を問わない連携が不可欠であり、グローバルな視点での推進力が求められる。これらの要素を統合し、当領域では柔軟かつ包括的に進化し続け、この領域のリーダーとして未来の健康課題に立ち向かうための基盤を築き続けていきたいと考えている。